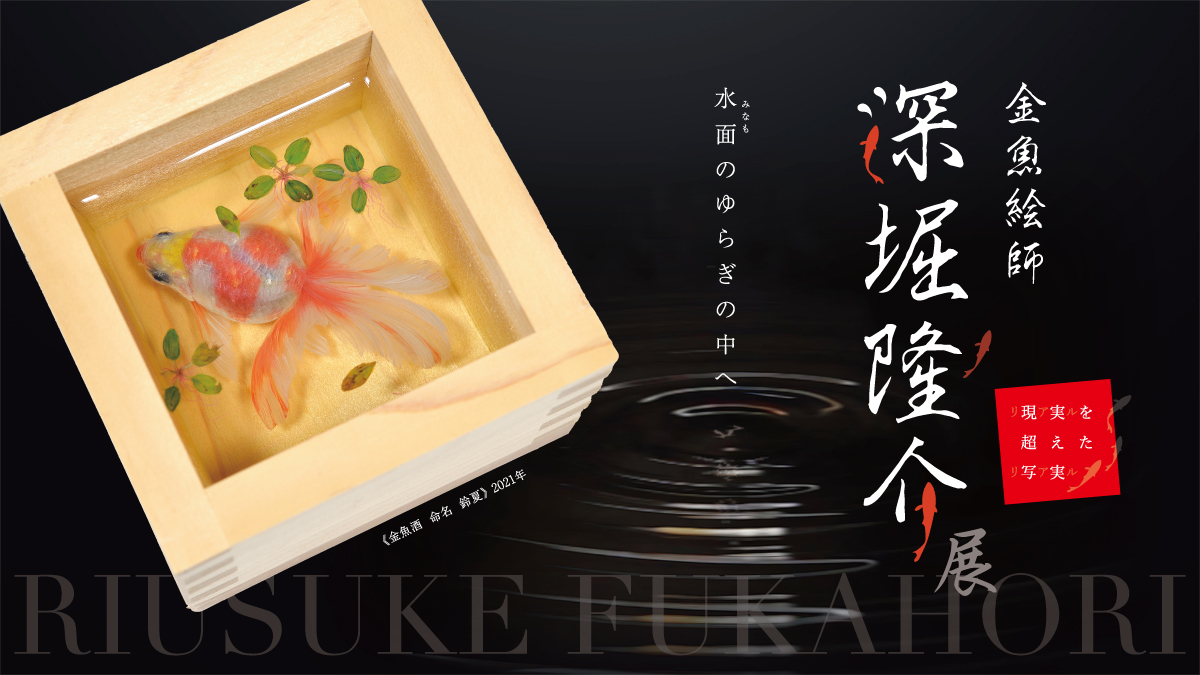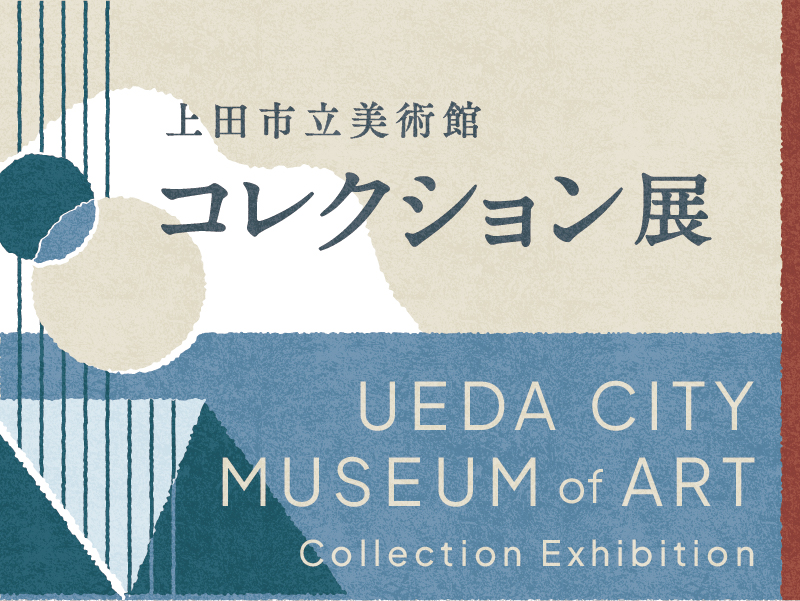【レポート】川久保賜紀 クラスコンサート
【レポート】川久保賜紀 クラスコンサート
2024年12月20日(金)
上田市立丸子中央小学校
ヴァイオリン:川久保賜紀
ピアノ:三浦友理枝
2016年度、2019年度に続き今年度のレジデント・アーティストをつとめるヴァイオリニストの川久保賜紀さん。ピアニスト・三浦友理枝さんとともに、上田市立丸子中央小学校の5年生へ音楽を届けました。12月20日(金)午前のクラスコンサートの模様です。
前日の1・2組に続き、この日は5年3組の25名が観客です。
子どもたちの期待がこもった拍手に迎えられたおふたりは、早速1曲目へ。チャイコフスキー(1840-1893)作曲『なつかしい土地の思い出』より「メロディ」を演奏し、クラス全体の意識を引き付けます。

温かみのあるメロディは、外の雪で明るさを増した音楽室の空気と調和しています。子どもたちは、音の振動が体感できるほど近い距離での演奏に、迫力を感じていました。
1曲目終了後の自己紹介で、おふたりは「ヴァイオリンとピアノの音色や、演奏中に私たちがどんなことをやっているのかを知ってもらえると嬉しいです」と、子どもたちに語りかけました。

ヴァイオリンの仕組みを説明すると、“ヴァイオリンの心臓”と呼ばれる魂柱(こんちゅう)に子どもたちは興味津々。見やすいように川久保さんがヴァイオリンを近づけると、みんなf字孔から中を覗きこみます。普段は見る機会のないヴァイオリンの内部に、驚きの声が上がりました。

レガート、スタッカート、ピチカートといった手や弓を使うさまざまな奏法を紹介して次の曲へ。
クライスラー(1875-1962)の『愛の喜び』『中国の太鼓』を続けて演奏します。川久保さんが使用するヴァイオリンは、かつてクライスラーが弾いたこともあるのだとか。華々しさと優しさが同居する曲調の『愛の喜び』。ヴァイオリンによる中国風のメロディと、ピアノの刻む太鼓のリズムが楽しい『中国の太鼓』。どちらも、ヴァイオリンの魅力がたっぷりと詰め込まれていました。

川久保さんは一旦掃け、三浦さんのピアノ・ソロが始まります。曲はフランスの作曲家・フォーレ(1845-1924)の『無言歌 第3番』。2024年はフォーレが亡くなって100周年の“フォーレ・イヤー”です。『無言歌』は、名前の通り歌詞がない曲ですが、歌のようなとても美しいメロディが特徴です。「どんな歌詞をつけるとよさそうか、想像しながら聴いてください」と言う三浦さんが、ピアノをたっぷりと歌わせるように弾きます。

川久保さんが再び登場し、ガーシュウィン(1898-1937)作曲の歌劇『ポギーとベス』から「何でもそうとは限らない」を演奏します。
ガーシュウィンは、クラシックにアメリカ発祥のジャズやブルースなどを混ぜ合わせたアメリカの作曲家として有名です。今回は、“ヴァイオリニストの王”と称されるハイフェッツ(1901-1987)がヴァイオリンとピアノのためにアレンジしたバージョンです。
川久保さんもアメリカで生まれ育ったため、ガーシュウィンにはとても馴染みがあるとのことでした。三浦さんが「これまでの曲とだいぶ雰囲気が違うので、その違いを楽しんでください」と言う通り、冒頭から一気に、アメリカ・クラシック音楽の世界へ誘われます。

思わず身体を揺らしたくなるジャジーな調べは、子どもたちにどう響いたでしょうか。
演奏を一休みして、質問コーナーです。たくさんの手が挙がります。
「ヴァイオリンを弾く時はどうやって支えているんですか?」「弦を弾いたり押さえたりして指が痛くならないですか?」「弓の毛が切れたらどうするんですか?」「いつから楽器をはじめたんですか?」など、次々に質問が飛び出しました。

最後はモンティ(1868-1922)の「チャルダーシュ」。哀感と情熱に揺さぶられる曲が、川久保さんと三浦さんの息の合った演奏で輝きます。前日のクラスコンサートでも、この曲がいちばん気に入ったという子どもたちが大勢いたそうです。

演奏が終わり、おふたりは大きな拍手で見送られます。
一流の演奏家と間近で触れ合える貴重な時間を、子どもたちも味わっていました。
【プログラム】
チャイコフスキー:『なつかしい土地の思い出』より「メロディ」
クライスラー:愛の喜び
クライスラー:中国の太鼓
フォーレ:無言歌 第3番(ピアノ・ソロ)
ガーシュウィン:歌劇『ポギーとベス』より「何でもそうとは限らない」
モンティ:チャルダーシュ