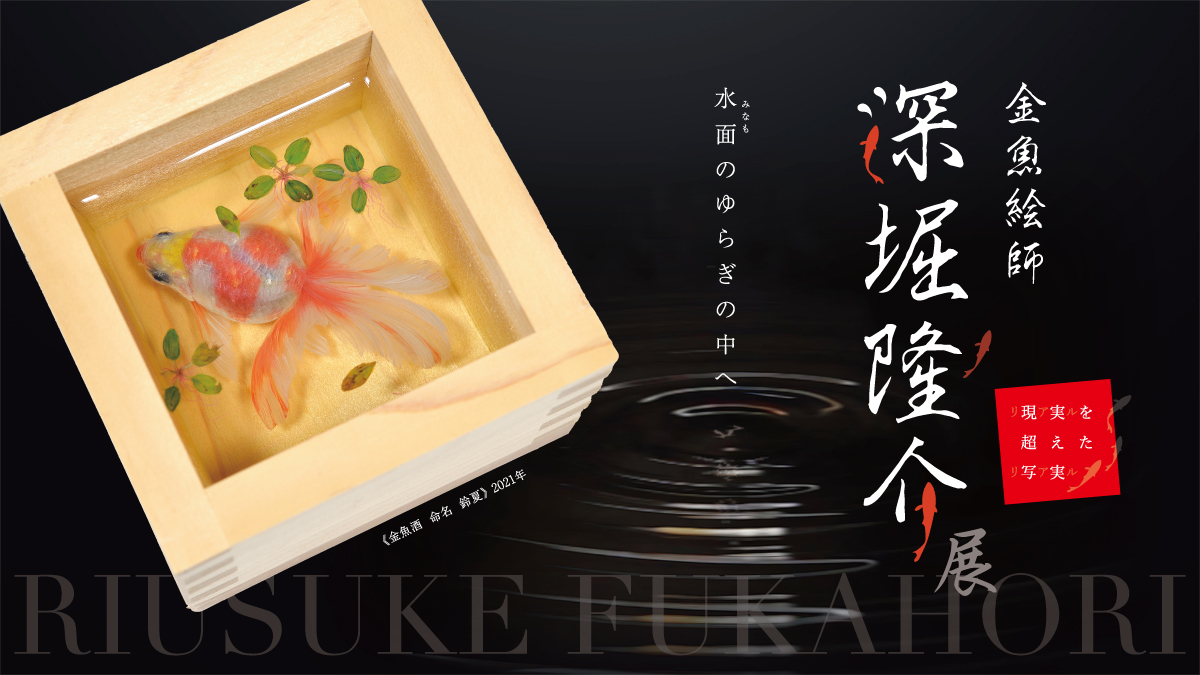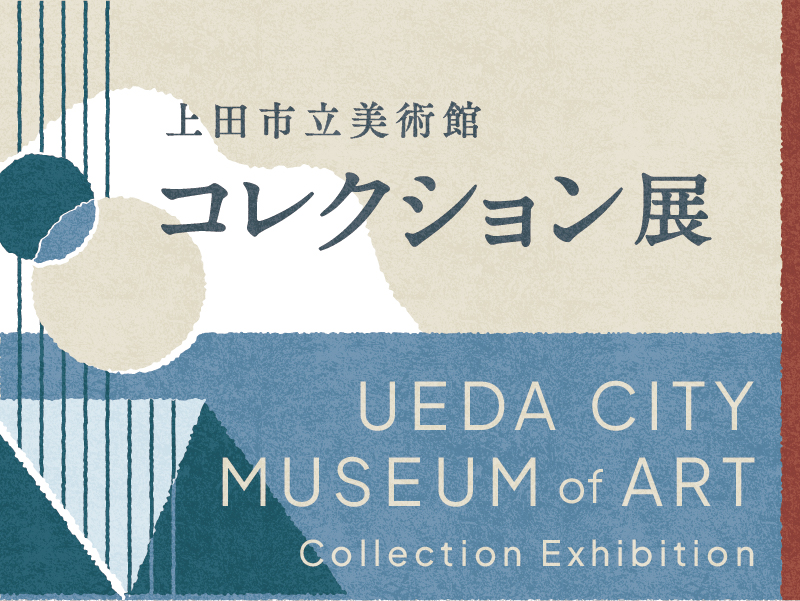【レポート】川久保賜紀 ヴァイオリン・リサイタル
- 開催日
- 時間
- 14:00~
- 会場
- サントミューゼ 小ホール
節分のこの日、今年度のレジデント・アーティストであるヴァイオリニストの川久保賜紀さんのリサイタルが開催されました。ピアノは、川久保さんにとって「もっとも信頼するピアニストであり友人」の三浦友理枝さん。息の合った演奏とトークに期待が高まります。
1曲目『プレリュードとアレグロ』の幕開けにふさわしい鮮やかな旋律が、川久保さんの透明感ある演奏で一層華やかに聴こえます。
曲が終わると、お二人はクラスコンサートを振り返ります。「子どもたちのエネルギーがすごくて、なんていい子たちなんだ! と感激しました。それに、大人っぽい鋭い質問をしてくれるんです」と川久保さん。続いて、今日がクライスラーの誕生日であり、今年は生誕150年という節目であることが明かされます。川久保さんのヴァイオリンは1762年製で過去にクライスラーが弾いていたこともあり、クライスラーとの縁が重なる日となりました。

つづいて、軽快さと親しみやすさにあふれた『愛の喜び』、ピアノが刻む太鼓のリズムの上をヴァイオリンが軽業師のように渡っていく『中国の太鼓』へ。
4曲目は、ガーシュウィンの歌劇『ポギーとベス』のアリアをハイフェッツが編曲したものです。まずはエラ・フィッツジェラルドなどの名手が歌い継いでいる『サマータイム』。ジャズやブルースに特徴的な音階”ブルーノート”が醸す切なさと会話のような掛け合いが、歌で聴くのとは違った趣です。『何でもそうとは限らない』では、ヴァイオリンが口笛のように響きます。
5曲目は三浦さんのソロでラヴェルの『亡き王女のためのパヴァーヌ』。ガーシュウィンはラヴェルに弟子入りを願い出ましたが、ガーシュウィンの実力を認めた上で断られます。ラヴェルの作品にはジャジーな雰囲気を持つものがあり、影響を受けていたのかもしれませんと三浦さんが話します。ラヴェル自身が管弦楽曲としても編曲しているピアノ作品で、三浦さんの演奏はどこか弦楽器のニュアンスがあり、粒立つような旋律に靄(もや)がかかった和音の残響が美しく、奥行と抒情性を感じました。
6曲目『エストレリータ』はメキシコ人作曲家・ポンセの作。ロマンティックな歌曲を、これまたハイフェッツが編曲しています。
前半最後はチャイコフスキーの『ワルツ・スケルツォ』。三連符の取り方はたとえばクライスラーと比較しても違いが際立ち、そこが聴きどころと言います。チャイコフスキーらしい美しさと繊細さに快活さが加わり、違う世界へ飛ぶようなヴァイオリンのソロ・パートが印象的でした。

後半はチェコの作曲家ドヴォルザークの『4つのロマンティックな小品』へ。清い川の流れのような第1曲、激しくスピーディーな第2曲、晴れた日ののびやかさがある第3曲、哀しげにはじまる第4曲と、キャラクターの違う小品集です。

最後はノルウェーの作曲家グリーグの『ヴァイオリン・ソナタ第3番』です。
第1楽章は雪の降る森を何かから逃れる厳しさと、過去の思い出を慈しむような温かなパートを連想させ、物語を感じます。第2楽章はロマンティックな導入と民族舞曲的な強いピチカートとのコントラストが際立ちます。第3楽章ではヴァイオリンとピアノの追いかけっこからはじまり、緊迫した場面、穏やかな場面をはさみ、ふたたび激しさを増して速いパッセージで終曲へ。
25分の熱演に、客席からひときわ大きい拍手と「ブラボー!」の掛け声が送られます。手を握りあう川久保さんと三浦さんは、輝くような笑顔で応えます。

アンコールの『チャールダーシュ』は、アドリブと余裕が感じられるほど川久保さんのものになっていて、とても情熱的です。さらに大きな拍手に、お客様の感動が込められていました。
お客様の感想です。
長野市から家族で来られた女性は、「夫が大ファンで、今日は姉妹を誘って来ました。グリーグが素晴らしかったです」。ヴァイオリンを習っているという高校2年生の女性は、お父様とご一緒に。「川久保さんは自分も弾いたことがあるクライスラーをとても素敵に演奏されていて、感動しました。あんな音が出せるようになりたいです」と話してくれました。
【プログラム】
クライスラー:プレリュードとアレグロ
クライスラー:愛の喜び
クライスラー:中国の太鼓
ガーシュウィン:歌劇『ポギーとベス』より「サマータイム」「なんでもそうとは限らない」
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ(ピアノ・ソロ)
ポンセ:エストレリータ
チャイコフスキー:ワルツ・スケルツォ
ドヴォルザーク:ロマンティックな小品 作品75
グリーグ:ヴァイオリン・ソナタ 第3番 作品45
【アンコール】
モンティ:チャールダーシュ
取材・文:くりもときょうこ
撮影:齊梧伸一郎