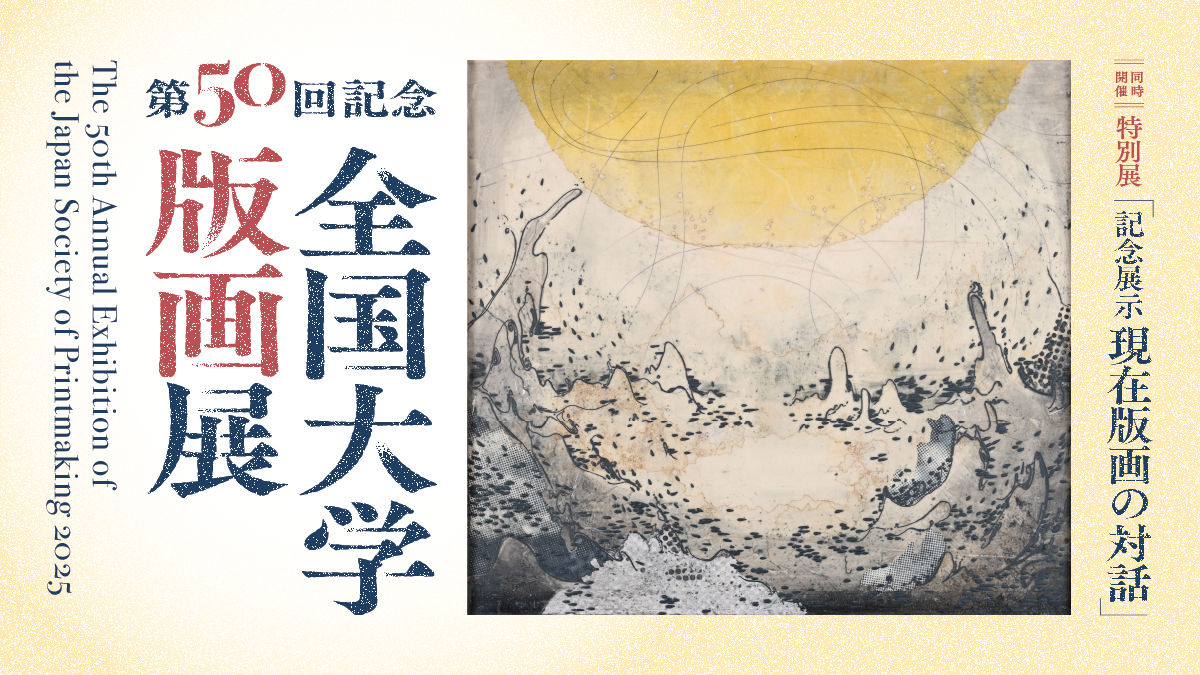【レポート】ロマン派症候群
- 会場
- サントミューゼ
ロマン派症候群
9月1日(金) 19:00~
9月2日(土)14:00~
at サントミューゼ小ホール
ショパンとブラームス。
ロマン派音楽をともに彩った、しかし生きた国も年代も違う二人の作曲家が、もしも病院で出逢ったら……。
そんな奇想天外なシチュエーションで幕を開ける「ロマン派症候群」は、二人の俳優の芝居と、三人の演奏家による生演奏が同じ舞台で繰り広げられます。

そこにあったのは「生演奏のBGMがある芝居」でも「クラシック音楽をセリフで解説する演奏会」でもなく、言葉と音楽という二つの表現で立体的に描き出す大作曲家の人間らしい心模様でした。
作・演出を「南河内万座一座」座長の内藤裕敬さん、音楽監修とピアノをピアニストの仲道郁代さんが務める本作品は、サントミューゼの自主制作作品として2016年1月に初演。
改定再演となる今回は、上田公演を皮切りに、10月8日の北九州芸術劇場での千秋楽まで、全国7都市を巡るツアー公演です。
初演に引き続き松永玲子さん(劇団ナイロン100℃)、坂口修一さんのお二人が役者として出演。
演奏はヴァイオリンに川久保賜紀さん、チェロに加藤文枝さんとソリストとして活躍中のお二人を迎えています。
舞台中央に一台のピアノ、その背後には何枚もの包帯とシーツがはためく物干し台。
およそクラシック音楽が語られるとは思えない不思議なシチュエーションで、幕は上がりました。

現れたのは、パジャマ姿の男と女。
長く入院しているという二人、女は自分の病を嘆き、悲観的で焦った様子。
いっぽうの男はというと病気の自覚症状は「まったくない」とあっけらかんとした調子で、「退院できないかな」と希望を持つ彼に「幸せな人だ」と呆れる女。
名前こそ名乗らないものの、会話の端々から、もしかすると女はショパン、男はブラームスではないだろうかと観る者に感じさせます。
二人は結局、最後まで名乗ることはありません。
そんな曖昧な状況だからこそ、彼らの言葉は単なる「解説」にならず、観客のイマジネーションをかき立てます。
たとえば、「今を作っているのは思い出だろ」と言う女に、「思い出に、今を邪魔されたくないんです」と返す男。
それはショパンとブラームスの会話とも想像できるし、そうでなくても、私たちが日常でふと感じる感覚とも重なります。
「もしかすると、ブラームスやショパンも私たちと同じようなことを感じたり、悩んだりしていたのかな」と、大作曲家に対して勝手に近しい気持ちを抱く感覚は新鮮で、これまで音楽室の肖像画の中の人に過ぎなかった彼らに、人間らしい熱や表情が宿ったようでした。
そんな舞台で鳴り始める二人の楽曲。
そこには作曲家の手ざわりのようなものが色濃く感じられ、豊かな感情や体温までも伝わってくるようでした。

車窓を通り過ぎる景色と思い出を重ね合わせ、「全てが通り過ぎてしまうことが怖い」と吐露する女。
その言葉を受け、闇を切り裂くように始まった「幻想即興曲」からは、ショパンの言葉にならない想いが立ち上ってくるようです。
何度も耳にした名曲ながら、ショパンの焦りや苦悩、祖国への想いといった輪郭を芝居から感じ取ったからでしょうか、普段と違う切実さを帯びて響き、いわゆる「クラシック音楽」という垣根を越え、そして数百年の時間を飛び越えて、今を生きる私たちの心に直接語りかけてくるようでした。

何より圧倒されたのは、芝居と音楽が呼応し合って生まれる一つの大きな空気です。
役者と奏者は、互いに言葉を交わすことはありません。
ただ同じ舞台に立ち、それぞれの表現を行います。
しかし演じる松永さんが「(舞台の)中で行われているのは戦い」とインタビューで語っていたように、そこには目に見えない想いの渡し合いがあるように感じられました。
役者が生み出した空気に呼応し、音楽という表現で返す。
その拮抗したやりとりが一つの大きなうねりとなり、受け手の想像をかきたてます。

匿名の芝居、そして言葉を越えた音楽。
受け手の自由なイマジネーションを刺激する豊かな余白があるからこそ、きっと100人いれば100通りの受け取り方が生まれるのでしょう。
幕が下りた後、これまで感じたことのないさまざまな感情や楽曲への印象が生まれたことに気づき、喜びを覚えるかもしれません。
今回の全国ツアーでは、それぞれの会場で役者と奏者、会場の空気が響き合い、その日その場所でしか生まれ得ない世界観となり、毎回違ったショパンとブラームスに出会えることでしょう。
写真:谷古宇正彦