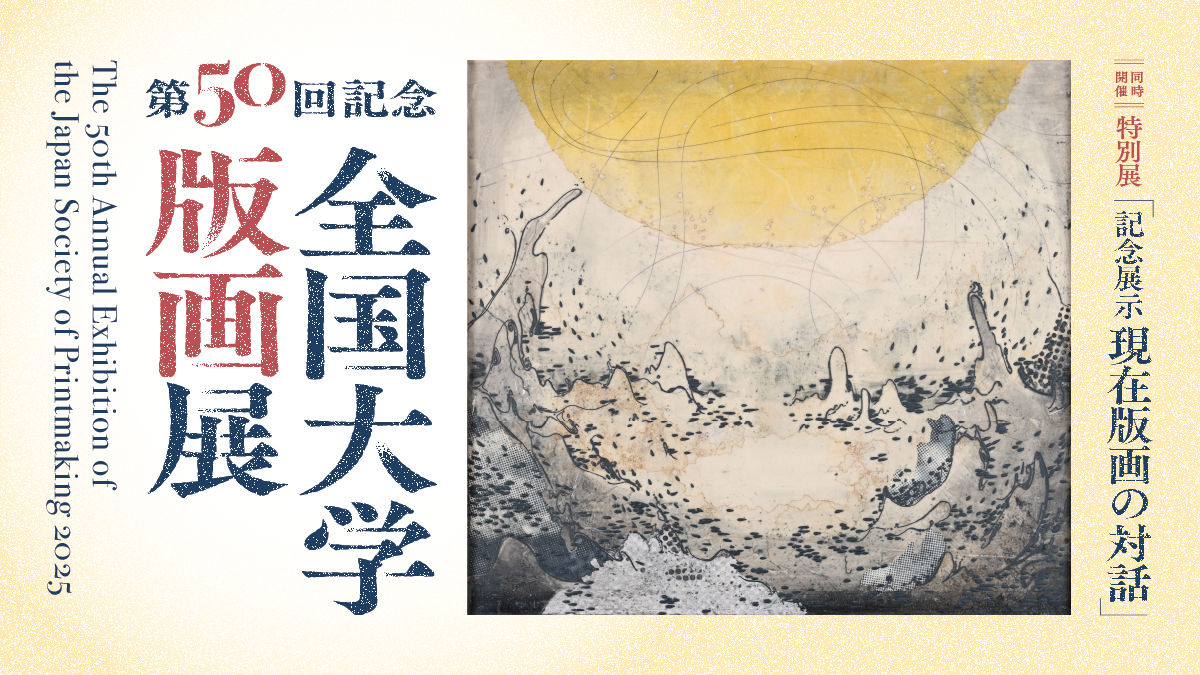【レポート】アナリーゼワークショップvol.38~ソーイチ・リーベ ブラームス
- 会場
- サントミューゼ
アナリーゼ(楽曲解析)ワークショップ vol.38
広島交響楽団上田公演 関連プログラム
「ソーイチ・リーベ ブラームス」
2020年2月19日(水) 19:00~20:00 サントミューゼ小ホール
3月15日(日)に開催予定だった広島交響楽団(以下、広響)の上田公演は、新型コロナウィルス対策のため残念ながら中止となってしまいましたが、2月19日(水)に広響の第一コンサートマスターを務めるヴァイオリニスト・佐久間聡一さんによるアナリーゼ・ワークショップを開催しました。その様子をレポートします。
今回のテーマは公演で演奏されるブラームス作曲、交響曲第1番。
ブラームスを「偏愛している」という佐久間さんが、その魅力をわかりやすく分析していきます。
平日の夜にも関わらず30人を超えるお客様が待つ会場に、ヴァイオリンを携えた佐久間さんと、ピアニストの池原舞さんが登場します。
今回はピアニスト・池原舞さんがピアノ伴奏をつとめました。
池原さんは音楽学者でもあり、楽曲解析は専門分野です。
そんなおふたりのコラボレーションで進めます。
まず、そもそも交響曲とは? というところから入ります。
英語でsymphonyと表記し、symは「共に」phonyは「響く」という意味があります。
「交響曲」という言葉を発明したのは森鴎外ですが、原語の意味をうまく捉えていることがわかります。

池原さんが、交響曲のルーツはイタリアのオペラに入っている「序曲(シンフォニア)」だと解説してくれます。サンマルティーニという作曲家がこの序曲を抜き出して演奏会で演奏したのがはじまりです。
さまざまな作曲家によって発展していき、“交響曲の父”ハイドンが活躍する古典派の時代には、交響曲の定義である「4楽章からなり、うち少なくとも1楽章はソナタ形式」が完成していました。
ハイドンは生涯で104曲もの交響曲をつくります。その後、モーツァルトが41曲、ベートーヴェンは9曲というように、時代が下るごとに“量より質”に変化していきます。
と同時に、交響曲はクラシック音楽の中で最高の地位と位置づけられるようになります。
とりわけベートーヴェンの交響曲9曲については、佐久間さんが「これがなかったら、僕たちはごはんを食べられません」というほど聴衆に愛され、演奏家にとっても重要な作品群となっています。
そのベートーヴェンのあとを嘱望された作曲家のひとりが、シューマンでした。
シューマンは生涯で4曲の交響曲を残し、古典派からロマン派、そしてその後の世代への橋渡しをしたと評価されています。
そのシューマンに絶賛されたのがブラームスでした。
初めて会った時にブラームスが弾いたピアノに驚いたシューマンは以降、妻クララと共に、ブラームスと親交を深めます。
佐久間さんは「ブラームスを語るのに外せない人が3人います。ベートーヴェン、そしてシューマンと妻クララです」と解説します。

3月の公演では、ブラームスの「交響曲第1番 ハ短調 作品68」が演奏されます。
21年もの歳月をかけて、ブラームス43歳の時に完成した作品です。
佐久間さんは「ベートーヴェンという偉大な作曲家がプレッシャーになっていたのかもしれない」と分析します。
まず、冒頭を演奏します。
オーケストラではティンパニ、コントラバス、コントラファゴットなどが奏でる低音の連打と半音で動く旋律は不協和音となり、聴く者の居ずまいを正すような力があります。
佐久間さんが
「冒頭にしてはテンションが高すぎると感じませんか?ブラームスは保守派だと思われていますが、僕はこのパートだけでも、本当に保守派なのかと感じるほど斬新です。ベートーヴェンも、さすがにこれはやりすぎだと怒ったかもしれません(笑)」
と解説します。

第2楽章を演奏して、複雑な和音と和声、長いメロディーで「明るいのに悲しい、どちらともとれる」揺れ動く繊細な感情を音楽で表現しているところが、ブラームスの“専売特許”だと言います。
そこをよりわかりやすく伝えるために、今度は池原さんのピアノに佐久間さんが口頭で和音の解説を乗せていきます。
「ブラームス愛」が溢れる佐久間さんの語り口により、感情が繊細に揺れ動く感じがよく伝わってきました。


第2楽章にはコンサートマスターによるヴァイオリン・ソロがあり、公演では佐久間さんの腕の見せ所となります。
池原さんに「どんな気持ちで弾いているんですか?」と聞かれた佐久間さんは「これは本当に複雑な気持ちで……」と心境を吐露してくれました。
コンサートマスターのソロは珍しくないのですが、通常はオーケストラもそれなりに音を出している状態でのソロパートが多く、外へ発散する感覚で弾けるそうです。
しかしこの曲については、内へ内へ思いを凝縮していくパワーが必要で、「とっても嬉しいけどすごく嫌」という相反する感覚に襲われると佐久間さんは言います。
続く第3楽章は、それまでの交響曲の歴史においては口直し的な位置づけで書かれていることが多いそうです。しかしブラームスは、田舎風の曲想でありながら2拍子で書くという独創性を発揮しています。「深刻ではないけれど、他にない不思議な響き」の特異な楽章です。
また、池原さんは調に着目します。
「面白いのが全体の調構造です。1楽章がハ短調なら2楽章、3楽章はこの調にするだろうというセオリーを外してきているんです。4楽章もそうです」。
この調は音楽用語で「メディアント調」と呼ばれ、シューベルトが好んで使っていた響きでもあります。
シューベルトは佐久間さんがブラームスの次に好きな作曲家で、この偶然の一致に目を輝かせていました。

この交響曲へのベートーヴェン、シューマン、クララの影響が、具体的にどこに盛り込まれているのかも触れます。
まず「ハ短調」という調。同じ調の交響曲といえば、ベートーヴェンの「交響曲第5番 運命」がすぐに思い浮かびます。
主題の主部は「交響曲第9番」の〈歓喜の歌〉に似ていると初演で指摘された通りで、実際におふたりの演奏を聴くと、ベートーヴェンへのオマージュを感じます。
第4楽章のホルンによる「呼びかけ」メロディーは、この曲が完成するより前に、クララへの誕生日プレゼントとして送った短い楽譜が出典となっています。
最後、テンポが上がって何度も和音を叩きつけるように盛り上がるところは、シューマンを思わせます。
佐久間さんが「まだまだ研究者も気づいていない秘密がいっぱい隠れているんじゃないかと思います」と言うように、敬愛する偉大な作曲家たちへのオマージュが散りばめられた交響曲です。
「古典的な様式を最後まで守り続けながら、心の中は爆発するようなロマンが渦巻き人間愛に溢れていた。ロマン派最後の金字塔を打ち立てたのがブラームスです」。
佐久間さんがなぜブラームスを敬愛しているのか、そしてバッハ、ベートーヴェンと並んでドイツ音楽史上の「3大B」と称される大作曲家である理由が、説得力をもって伝わってくるアナリーゼでした。